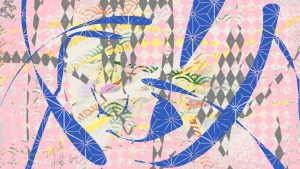20才代の女性患者Cさん。昨年末にボルダリング(崖登り)の練習を始めた瞬間に、左膝外側靱帯を伸ばしてしまいました。病院で膝のサポーターを作り、山登りをすることは出来ますが、正座は出来ません。仰向きの状態で左膝を伸ばすのが怖いそうです。
今日で3日連続の来院です。Cさんこの2日間で左膝の伸展、屈伸がずいぶん楽になっています。今日も、ベッドで仰向けになってもらいます。左脚が1.5cm短くなっています。Cさんをよく観察すると、左胸部が張っています。そこで、軽く左胸部を押圧するだけで、かなりの痛みを訴えるCさん。その後、左肘も押圧。
「これだけで、かなり(両脚が)そろってきましたね。」
Cさんは、患部を触れないで遠隔の部位を刺激するだけで、カラダが整うこと理解してくださいました。その後は、Cさんの感覚を大切にします。
「今日は、鍼とお灸・・・どっちがいいですか?」
「お灸かな・・・」
ということで、足にお灸。これだけで良くなるのです。この理論はいずれ説明いたします。
Cさん、ずいぶん良くなりました。2日後の予約を受けました。次回が楽しみです。