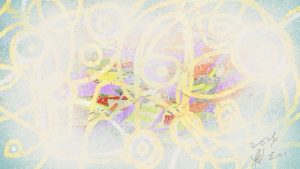山元式新頭鍼療法(YNSA)と操体法の融合?
昨日のFacebookで紹介した60才代の男性患者Bさん、左膝が痛くて引きずりながら歩いて来院されました。左右の肘を押圧するだけで左膝痛が無くなったのですが、これには山元式新頭鍼療法(YNSA)と操体法の融合だったのかもしれません。
YNSAでは、肘は同側の膝の治療点として習いました。操体法では、膝を悪化すると対角(左膝ならば右肘)に負荷がかかるので、対角の肘から治療するとなります。その後、時間の経過とともに、右膝→左肘と治療する個所を移すようになります。
先日のBさんは、仰臥位になった状態をYNSA、操体法の色メガネを掛けないで、透明な目で見ました。すると気になるのが右胸郭。そこで、押圧すると今度は右肘が気になり押圧・・・・すると、今度気になるのが左肘、そして押圧。
という経過がありました。よくよく考えてみると、やはり操体法の治療法の通り左膝の負荷が、右の体幹に影響を与えていたのかもしれません。そして、対角の右肘がゆるむと、同側の左肘の負荷が表れてきたのかもしれません。今後とも、左右の肘膝の関係をしっかり検証していこうと思います。