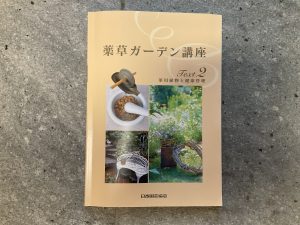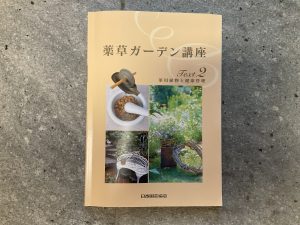今や世界中から注目されているエンジェルスの大谷翔平選手。4回投げ途中で痙攣を起こし降板となりました。最近、痙攣というアクシデントが多いので、その原因を調べてみました。ご本人は、疲れているからだとおっしゃっています。もちろん、その通りだと思います。そこを、もう少し深掘りしてみました。
『肉のけいれんの最も一般的な原因は以下のものです。
明らかな理由なく起こる脚の筋肉の良性のけいれん(典型的には夜間に発生する)
運動に伴う筋肉のけいれん(運動中または運動後に発生する)
筋肉のけいれん(「筋肉がつる」とも表現されます)は、健康な人にもしばしば起こり、通常は中高年の人によくみられますが、ときに若い人に起こることもあります。筋肉のけいれんは、激しい運動の最中や後に起こる傾向がありますが、ときに安静時にも起こります。就寝中に脚の筋肉に痛みを伴うけいれんが起きる人もいます。 睡眠に関連する脚の筋肉のけいれんは、ふくらはぎや足の筋肉に起こることが多く、その場合は足や足指が下方へ屈曲します。このような筋肉のけいれんは、痛みを伴うものの、通常は良性の(重篤でない)けいれんです。
筋肉のけいれんは、ほぼすべての人に時折みられる現象ですが、特定の異常があると、けいれんのリスクや重症度が高まります。具体的には以下のものがあります。
ふくらはぎの筋肉の張り(ストレッチの不足、運動不足、ときに下腿への体液の蓄積[浮腫と呼ばれる]が繰り返されることなどに起因する)
脱水状態
血液中の電解質(カリウム、 マグネシウム、 カルシウムなど)濃度の低下
神経の病気または 甲状腺機能低下症(甲状腺の活動が不十分になった状態)
特定の薬剤の使用
電解質濃度が低下する原因として、一部の利尿薬の使用、アルコール依存症、特定のホルモン(内分泌)の病気、 ビタミンD欠乏症、体液の喪失(とそれに伴う電解質の喪失)を引き起こす他の病気などがあります。電解質の濃度は、妊娠の後期にも低くなることがあります。』
『レースやトレーニング中に筋肉が激しく収縮するけいれんは、カリウムやナトリウム(塩分)、マグネシウムなどのミネラルが、汗と共に排出されたために体内のミネラルバランスが崩れ、筋肉の収縮と弛緩がうまくいかなくなった結果起きる。ナトリウムは、通常の食事をしていればほとんど不足することはないが、ハードトレーニングなどで大量の汗をかいた時は意識して補給する必要がある。
■カリウム
【効果的なとり方】
カリウムは体内ではほとんどが細胞内液に存在しているが、よくけいれんを起こすランナーは、日頃から果物を意識して食べるなど、カリウムを多く含む食生活を心がけるとよい。
【多く含む食品】
緑黄色野菜、ドライフルーツ、果実類(特にバナナ、メロン、アボカドなど)
■ナトリウム【効果的なとり方】人間の体内ではナトリウムとカリウムは1対1の割合で存在し、ナトリウムの多量摂取はカリウムの低下を招く。ナトリウムのとりすぎは高血圧の原因になるが、汗を大量にかくランナーは多めにとる必要があり、特に夏場は気をつけたい。
【多く含む食品】
ほとんどは食塩(塩化ナトリウム)として摂取される。
■マグネシウム
【多く含む食品】
アーモンド、魚介類、海藻類、豆類など』
とあるので、暑い夏で投手とバッターの二刀流は、大量の汗が出るためカリウム、マグネシウム、カルシウムなどが減り痙攣を起こしたようです。でもそれは、良性の痙攣なので心配することはないようです。