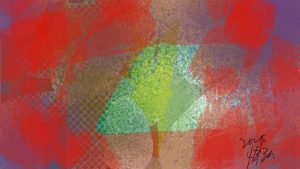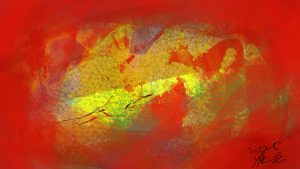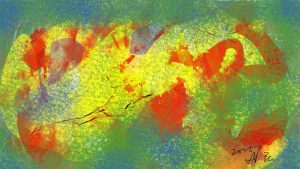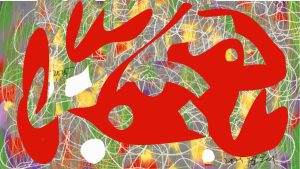新学期が始まりました。受験準備であまりカラダを動かしていなかったのに、急にスポーツの部活を始めると肉離れをおこしたりします。そこで、肉離れの時の対処法を、コピペします。よく知られているRICE処置です。
『RICE処置とは、肉離れや打撲、捻挫など外傷を受けたときの基本的な応急処置方法。Rest(安静)・Icing(冷却)・ Compression(圧迫)・Elevation(挙上)の4つの処置の頭文字から名付けられました。早期にRICE処置を行うことで、内出血や腫れ、痛みを抑え、回復を助ける効果があります。
1. Rest(安静)
ケガをしたら、まずは安静に保つことが大切です。安静とは、必ずしも横にして寝かせるとは限りません。むやみに動かすと悪化してしまう可能性があるので、患部にタオルや添え木などを当てて固定します。
2. Icing(冷却)
患部を氷や氷水などで冷やします。体温を下げることで、患部の毛細血管が収縮して、腫れや内出血、痛みなどが抑えられます。ただし、冷やしすぎると凍傷になるリスクがあるので注意しましょう。
具体的には、氷を氷のうやビニール袋に入れて患部に当て、20〜30分ほど冷やします。ピリピリとした痛みが出たあと無感覚な状態になったら、一度氷を外してゆっくり皮膚感覚を取り戻します。そのあと再び氷を当てましょう。これを何度か繰り返します。
3. Compression(圧迫)
患部にテープなどを巻いて圧迫し、腫れや内出血を最小限に抑えます。きつく圧迫しすぎると血流障害や神経障害を起こしますので、しびれや変色が生じたらすぐに緩めましょう。
4. Elevation(挙上)
患部を心臓より高い位置に保ちます。血液が心臓に向かって流れるので、内出血による腫れを防ぐことができます。患部の下に座布団やクッション、たたんだ毛布などを敷くとよいでしょう。』
ここで3. Compression(圧迫)の理由は、以前紹介した傷が治るシステムと多いに関係していると思います。少し長くなりますが、以前に書いた傷が治るシステムを記載します。興味ある方は、お読みください。
『傷が治るシステム
①皮膚に切り口が発生した。傷はV字に開いている。
②すると、まず切断面に神経ネットワークが形成される。
③そこに、第一次治癒電流が流れる。
④その指令で、切断面の体細胞が万能細胞に変わる。
⑤テープか縫合で、切断面を合わせる。
⑥第二次治癒電流が流れる。
⑦各部の万能細胞に各々の周波数刺激を与える。皮膚、筋肉、骨など固有周波数に従い、万能細胞は体細胞に戻る。
⑧こうして各体細胞は切断前と全く同じように再生治癒する。』
これは、トカゲ再生の謎を解いたロバート・ベッカー博士のベッカー理論です。ベッカー博士の「クロス・カレント」という著書を翻訳された船瀬俊介氏が、自身の書かれた「未来を救う波動医学」という本からの引用です。
傷口を圧迫することで、第二次治療電流の早期誘導を促すことになります。これが大事!