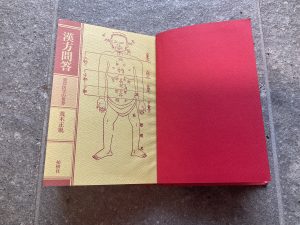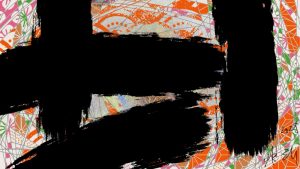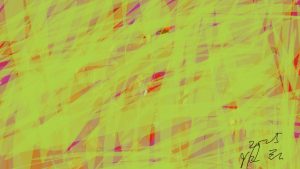ペンキを塗った缶に穴48個空け、腐葉土を入れ人参を育てました。この人参を乾燥させ、ミキサーで粉々にしたのです。ただ、葉っぱと根の部分の乾燥状態が違ったので、冷凍庫で保存することにしました。次回からは、葉っぱと根を切り離し、根も輪切りにして乾燥しなければならないと、分かったのです・・・・考えてみれば、当たり前なのですが、やってみないと分からないものです。そこで、生の人参と乾燥した人参、葉っぱと根っこどちらが、栄養素あるか調べてみました。
まず根っこ
『栄養も豊富で、ビタミンB1・B2・C、カリウム、食物繊維も多く含まれています。 カロテン類が豊富で、根菜類では唯一の緑黄色野菜に分類されています。にんじんは強い抗酸化作用を持つβカロテンの含有量が緑黄色野菜の中でも群を抜いています。 そのため活性酸素除去や抑制に効果的で生活習慣病の予防に役立ちます。 また、βカロテンは必要に応じてビタミンAに変換されます。 それによって皮膚や粘膜の組織を正常に保ち、結果的に美白・美肌作りと感染症の予防効果が期待できます。』
生と乾燥の栄養素の違い
『野菜を干すことで水分は蒸発しますが栄養素はそのまま残るため、生野菜よりも干し野菜の方が栄養価は高くなります。また、ビタミンDやビタミンB群、カルシウム、鉄分、ナイアシン、食物繊維などの栄養素は干し野菜にすることで含有量が上昇することが分かっています。』
次に、葉っぱと根っこはどちらが栄養価が高い?
『人参の葉っぱに含まれる栄養を、根の部分と比較したのでご覧ください。
可食部100gあたり
たんぱく質 カリウム カルシウム 鉄 βカロテン ビタミンE ビタミンC 葉酸
人参 葉っぱ 1.1g 510mg 92mg 0.9g 1700µg 1.1mg 22mg 73µg
皮なし人参 生 0.8g 270mg 26mg 0.2g 8300µg 0.5mg 6mg 23µg
人参の主な栄養を比べてみると、根より葉っぱのほうが含有量を多く含んでいることがわかります。
βカロテンは根のほうが多いものの、葉っぱも野菜の中ではトップクラスです。
栄養豊富な人参の葉っぱを、ぜひ料理に取り入れましょう。』
とあります。つまりは、人参に捨てるところなし!乾燥すればもっと良いという結論に達しました。