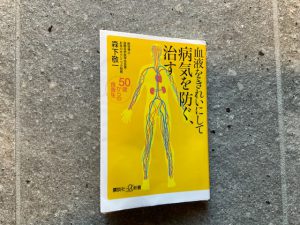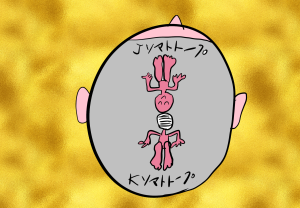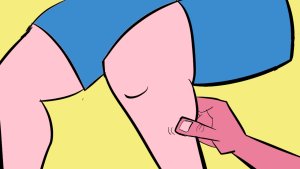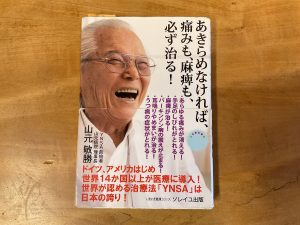1日1食の生活をし始めて、1年くらいは経ったと思います。おかげで8kgくらい体重が減って、ヨガ行者のような体型になってきました。この体型での動きはいたって軽いのです。先日の「のボール野球」でも無理のない動きが出来たように思います。さて、今年は柿が豊作なのでしょうか?患者さんから美味しい柿を沢山いただいています。1日1食でも、果物だけは時々食べることは、あったのですが、こんなに沢山の柿が一度に手に入ると、ついつい食べてしまいます。
夕方になって空腹感がないのは、私にとって普通ではありません。気持ちが悪くなります。食べ過ぎはよくないのが分かります。
今年は、熊が里に下りて来て人を襲う出来事が各地で起こっています。私が京都の山奥の美山町に住んでいるころ、熊に直接出会うことはありませでしたが、熊の目撃情報は頻回にありました。ある日、朝起きて庭の柿の木を見た時です。
「・・・・うん?今まであんなにあった柿がない!・・・どしたん?」
よくよく柿の木を見ると、引っ掻きキズが目のやや上にあります。熊が上った跡です。そして、横に小屋があり、その板間には、
「あれ?足跡🐾が・・・・しかも、親子の足跡!」
一夜にして鈴鳴りの柿を、親子熊に食べられました。冬眠前の熊は、食い溜めをするようです。熊との遭遇がなかっただけでも、幸いと思うようにしたのを覚えています。
その昔、里山には、屋根の葺き替え用の茅場があり、そこが明るいので熊や鹿は里山に下りてくることはなかったのですが、茅場に杉の植林をしたため、熊が身を隠す場所になってしまいました。
また、杉が多くなった山には、ドングリが無くなり、益々熊が里山に下りて来ている・・・何とかならないのかな・・・