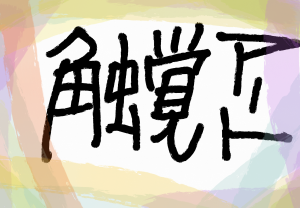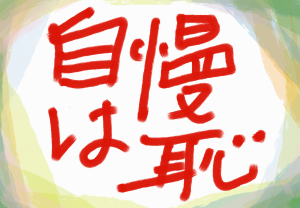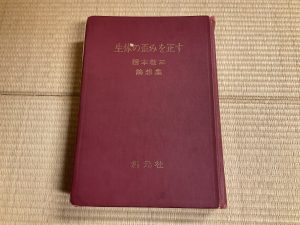患者さんから多くのことを学びます。今日は、テルミー療法について学びました。40才代の女性患者Bさんが、足首に虫刺されから湿疹のようなもの出来、かゆみに耐えられないほどだったのに、友人から受けたテルミー療法の2日後にすっかり治ったそうなのです。そこで、テルミー療法を調べてみました。下記の通りです。
『 「テルミー」とは、ギリシャ語で「温熱を利用した療法」を意味しています。
歴史は古く、1910年から約20年にわたる実験・研究によって、1929年(昭和4年)に発明されました。すでに70年以上の歴史がある民間療法なのです。
自然治癒力をたかめる家庭健康療法
テルミーの温熱刺激は、自律神経系・内分泌系・免疫系の働きを調整して、生命を維持する機能(ホメオスターシス)や自然治癒力をたかめることを目指しています。
また、血液やリンパ液の流れを促進させ、疲労回復や筋肉のこり等を癒し、消化器系の働きを活性化させる効果もあります。
つまり、心とからだの両面から自然治癒力に働きかけて、病気の予防、疲労回復、健康増進を目的とした家庭健康療法です。
安らぎを与え、誰にでもできて安全
誰にでもできる・・・子どもやお年よりにもかけてあげられます。
家庭でできる・・・自分自身でできます。もちろん家族同士でかけ合うこともできます。
操作が簡単・・・わずかな練習時間で誰でも扱えます。また、医学知識や経絡・経穴(ツボ)を知らなくてもできます。
安全である・・・副作用がなく、薬剤等との併用もさしつかえがありません。
気持ちがよい・・・テルミーの温もりは優しくおだやかで、リラックス効果もあります。
テルミー療法の行い方
使い方の基本は撫(な)でること
テルミー線(数種類の植物成分からできた線香状のもの)にロウソクなどで点火します。
冷温器(万年筆大の銅でできた筒状のもの)の中に入れます。
冷温器2本を1セットにして体表(皮膚・血管・リンパ管・神経・筋肉など)を刺激します。
刺激の方法は、皮膚を撫(な)でたり圧(お)したりすることによって器械的な刺激と温熱刺激を与える方法や、皮膚に直接触れずに熱や煙、光の刺激を与える方法などがあります。ぜひテルミーのおだやかな温もりを体験してください。
テルミーが考える「健康観」
私たちの心とからだには、生まれながらに健康を回復させる力が備わっています。それは「自然治癒力」と呼ばれる力です。
病気は、自然治癒力より病気の悪化力が大きくなったときにおこります。 現代医学の治療は、薬物その他の方法により病気をおさえ健康を回復しようとしますが、テルミー療法では日ごろから自然治癒力をたかめることによって健康を維持しようと考えています。
病気になってから手当をするのではなく、病気に負けないからだづくり、つまり病気を未然に防ぐことを大切にしています。とはいえ日ごろから健康に注意していても、病気やケガをしてしまうこともあります。そんなときテルミー療法は、部分的に治そうとするのではなく“心とからだ”の両面に働きかけ、少しでもはやく健康になるように自然治癒力の機能をたかめようとします。
幸せな人生は健康から生まれます。しかし、人にはそれぞれの人生観があるように、健康に対する考えもそれぞれ違います。イトオテルミー親友会は本療法を基本に、健康について会員の皆様と一緒に考えていきたいと思います。
それぞれに理想の健康観を確立して幸せな人生をおくりましょう。』
私にあっている気がします。山元式新頭鍼療法に取り入れることも可能かもしれません。楽しみ!