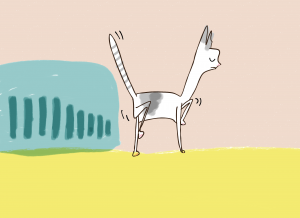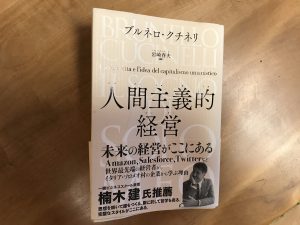
読書嫌いの私が、2日間で読み終え、じわじわとした感動に浸っています。
人間主義的経営 ブルネロ・クチネリ 翻訳 岩崎春夫
この本は、古代、中世からの叡智、遺産を未来に託し、生き生きとした文化、経済、教育、芸術を生み出した地方再生の羅針盤です。しかも、私と同年代のブルネロ・クチネリ氏の自叙伝から始まる田舎生活は、私の幼少期とも重なり、大家族の人間模様、生き様が美しく描かれ、共感しっぱなしでした。
ブルネロ・クチネリは、1978年、色鮮やかなカシミヤセーターを製造する小さな会社を立ち上げ、事業の目的を、倫理的にも経済的にも人間の尊厳を追及することと定めました。1985年ソロメオという小さな村の廃墟となっていた城を買い取り、「人間のための資本主義」を実現する場所とし、ブルネロ・クチネリ社の本社にします。
そして、ソロメオ村の豊かな暮らしを取り戻すため、村を修復し、文化、芸術、人々の交流を促進するために、劇場、図書館、公園などの施設を整備しました。
詳しくは、本を購入してゆっくりと読んでいくことをお勧めします。それにしても、翻訳が何と素晴らしい事か!!
大学時代の親友・・・・岩崎春夫氏は、同じ野球部で体育専門学群所属ではなく、比較文化を専攻。私は芸術専門学群だったこともあり、お互い変わり者同士。野球練習後は、彼の部屋が飲み屋状態でした。すると、比較文化の仲間が遊びに来て・・・・と、お陰で色々な人との交流が出来ました・・・皆んなどうしているんだろう・・・
岩崎春夫氏は、超エリート商社マンでトップに上り詰め、現在はHOP株式会社を設立。「美しく強い会社を創る」を目標に、ベンチャー企業や世代交代期を迎えた企業を対象とする人と組織の基礎作りを行う他、人事と経営の本質を学ぶ学校「人事の寺子屋」を運営しています。
下記は、岩崎春夫氏の訳者あとがきの一説です。
ビジネスの世界で働くことで世の中を今より良いものに変えていきたい。そう考える有意の経営者、企業で働く人々、そしてこれから社会に出る若者たちが、この本を読んでビジネスと経営について学び、ひとつでもふたつでも良い会社、美しい会社を作り出していって頂けたら、これほど嬉しいことはありません。そんな一つひとつの小さな会社の活動が、世界を覆う歪を治癒し、社会をもう一度良い方向に変えていく流れにつなげていくと確信します。