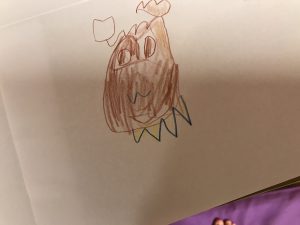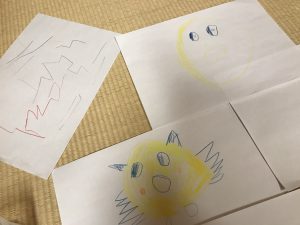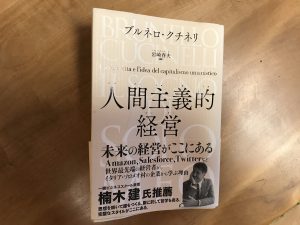j
j
『2021年度リーグ戦ネット配信を、首都大学野球連盟YouTubeチャンネルに加え、スポーツブルの特設ページ及び、UNIVAS公式サイトより1部リーグ戦全試合を無料ライブ配信をすることとなりました。』
上記の案内が、首都大学リーグ4月10日開幕に合わせて、メールで届きました。
何と、母校(筑波大)の試合をライブで見ることが出来るのです。
私がやっていた頃から・・・・もう40年も経っています・・そうか、ならば、こんな時代になってもおかしくは無いですね!首都大学リーグは、学業との両立を目指して試合は、土日に行います。我々が現役の時は、たしか川崎球場を使用していたように思います。
早速、午後3時から始まる筑波大学VS武蔵大学の試合観戦(大田スタジアムでの第3試合目)。
筑波大学のユニフォームが変わり、我々が着ていたユニフォームに少し似ているので、嬉しくなりました。40年前の武蔵大学は万年2部で、しかも下位チームでしたが、いまでは1部で優勝を狙えるチームへと変身していました。東海大菅生高校のバッテリーが主軸になっており、福島県の甲子園常連高、聖光学園出身の選手も入っています。
筑波大学は、身長181cm、体重83kgの佐藤隼輔投手(左腕)はドラフトでも注目される逸材。捕手の成沢選手は甲子園で優勝した東邦高校のメンバー。十分優勝を狙えるチームとなっています。
このライブ発信のアナウンサーが筑波大の野球部選手で、3試合とも続けて出演しています(朝から夕方までしゃべり散らし)。そのエネルギーには、ただただ敬服しました。このアナウンサーと、対戦する2チームの選手がゲスト解説でチームメイトの事をしゃべるので、楽しい時間を過ごせました。
試合結果は、1対0で筑波大学の勝ち。明日もあります。こんな楽しみが私の人生に突然生まれるなんて・・・・OB会事務局長はじめ、諸先輩方、関係者の方々に心より感謝いたします。