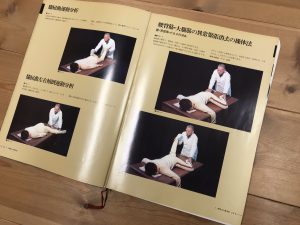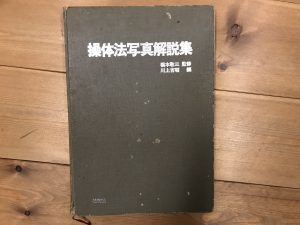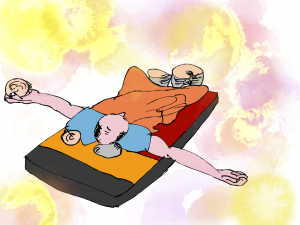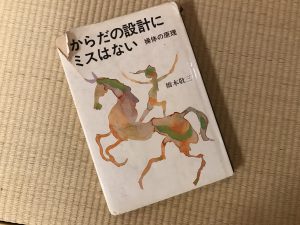何の根拠もない話。
最近の治療では、クスノキの瘤(こぶ)を、ベットに並べる事が多いのですが、あまり違和感を感じないのです。
もし、ただの木っ端を置くだけなら、違和感があるはずです。
なぜなんだろう・・・っと、ガイコツ(治療室にポツンと立ってます)を眺めながら、考えました。
木の瘤は、枝が折れた後、その周辺の樹皮が傷跡を覆(おお)った結果です。そんな瘤は、骨
と骨の境い目の関節に形状が似ています。
骨がまっすぐ伸びて折れた後、
「いや~~、俺はまっすぐ伸びたくない❣️動きたい・・・」
と骨が思ったなら、瘤(こぶ)を作って動きやすい形状になると思います。
つまり、次へのエネルギーを必要とする時、瘤(こぶ)が必要になるのです。
まあ~~、勝手な屁理屈です。
そんな瘤にふれることで、私は人体における骨、そしてそのエネルギーを感じます。
患者さんも私と同じようなエネルギーを感じるのではないでしょうか?
何の根拠もない話。

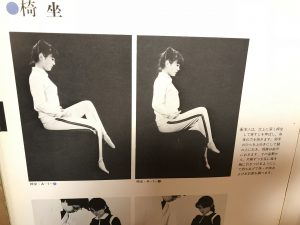 (つづく)
(つづく)