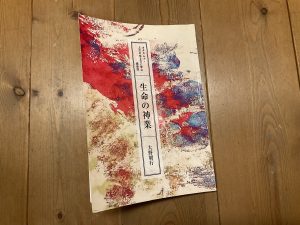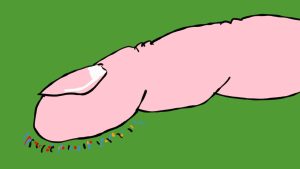オリンピックと共に、全国高等学校野球選手権大会も開催され、猛暑の中、連日熱戦が繰り広げられています。野球を愛する人として、気になることが2つあります。
1つ、入場行進。
なぜ、指をグーにして歩く?・・・・全く、不自然な行動です。手は部分ではありますが、全体も表しています。カラダ全体がノビノビ動きたいのに、なぜ指をグーにして萎縮した表現をするのですか?
私なら「ノビノビ手を伸ばして気持ちよく歩け!」と言います。カラダが伸びやかに動こうとする時、屈筋を縮める動きをし続けると、カチンコチンのカラダになってしまいます。そんな「私は緊張しています!」という表現は、必要ありません。
2つ、1塁へのヘッドスライディング。
こんな危険で、非合理的なスライディングは、今すぐ辞めさせるべきです。見ていて非常に不快です。1塁への最速は走り続けること。オリンピックの100m走で、誰がヘッドスライディングしますか?誰もしません!・・・・なぜなら、非合理的だからです。
私ならヘッドスライディングした選手は、試合に出させません。危険です、責任持てません。