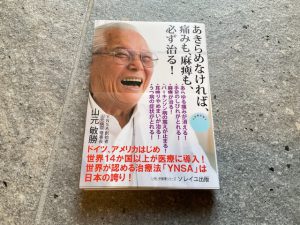
山元式新頭鍼療法(YNSA)の初級セミナーを受け、頭に置鍼をし始めた頃、70才代の男性患者A
さんのバイクが壊れ、Aさんは来院出来なくなりました。それから4年程経ち、やっと来院出来るようになりました。その間、コロナ禍もありAさんも人に会う機会が少なかったそうです。移動手段がなくなり、コロナ禍だとやはり、籠(こも)ってしまいます。久しぶりに会うAさんの笑顔を見ると嬉しくなりました。Aさんは、以前のように服を着替えようとするのですが、
「Aさん、もう着替えをしなくていいんです。」
「あああ、そうなんだ・・・・着替えるつもりで来てたのに・・・」
「この待合室で治療しているんです。」
「そうですよね・・・・最後の頃は、ここで頭に鍼刺すことがありました。」
私の場合、YNSAを習い始めてからなるべくYNSAだけで治療を始めました。その理由は、即効性があるからです。この即効性のおかげで今までの治療時間の半分に短縮出来るようになったのです。
「あれから随分進化して、お灸で足だけのYNSAや、鍼もお灸も使わないで指を当てるだけの治療もしています。」
と、4年間の変せんをさりげなくお伝えしました。
「先生、あの頭の鍼で花粉症が治りました・・・あの治療点に刺激すると、首の方に気持ち良さが走ったりするので、しょっ中やってました。」
「あああ、それは良いですね・・・・Aさんは感覚がすごいので、こちらが本当に勉強させてもらっています。」
などと、会話をしながら治療に入っていきます。Aさんは、言語能力に優れており、カラダに起こる感覚の変化を瞬時に表現してくれます。その能力の素晴らしさをお伝えすると、
「いやいや、私は普段は全く話さないんです。特にコロナ禍になって人と会うことがなくなったでしょう・・・・すると、ノドがおかしくなるんです・・・こういう時、ハーモニカを吹くと元気が出て来て、ノドもよくなるんですよ・・・ばあさんじいさんが、お経を読んでいる意味が、やっとこの年になって分かってきました。お経読むのは、タダでしょう?これ、カラオケに行って歌おうものなら、お金がいるじゃないですか・・・・世の中はうまい具合に出来ているんですよ。」
「なるほど!」
「今まで喋ってない分こうやって、いくらでもしゃべることが出来るんですよ。」
「なるほど・・・」
などと、話が続いていくのです。 (つづく)










