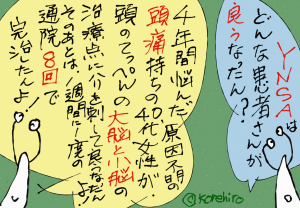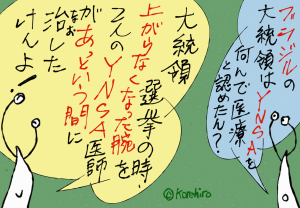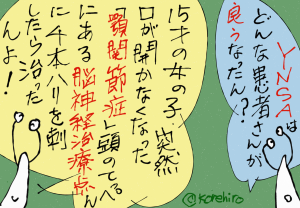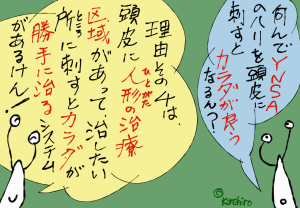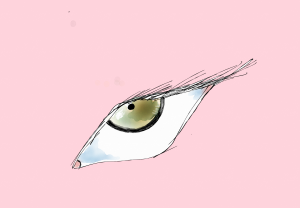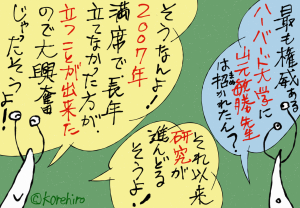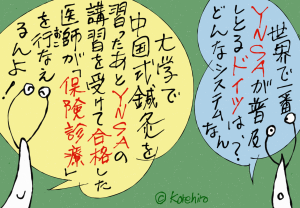患者さんから、「野菜は昼の4時間の日差しより、朝日からの2時間の方を好む」と教えていただきました。また、「西日は嫌い」ということも・・・ということは、道路をはさんで家が立ち並んでいる我が家の東側は、結構大きな駐車場があり冬でもそこからは、朝日が2時間は当たる場所があります。また、我が家の西側には小高い山があるので、西日は当たりません。ということは、野菜作りに結構適しているかも?・・・・と、考え直したのです(冬は、3階建てのアパートの陰で9割は日が当たらないので、あきらめていたのです)。
(私の師匠・加藤直哉先生がよしりんと対談されています)
冬の朝だけ日が当たる場所は、木の根っこを退治出来ず、3年前から桜の落ち葉を堆積するだけにして、放っておいたのです(何ともったいない!)。幸い、立派な腐葉土となっていました。この腐葉土に触れて、「ここで植物が育ちそう!」と感じたので、畑の大改革をすることになりました。
多分、今月中にはある程度出来上がっていると思います・・・次回のご報告は、完成した時にいたします!