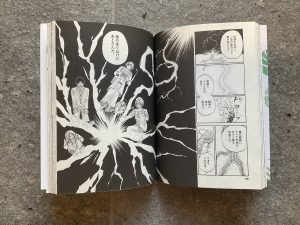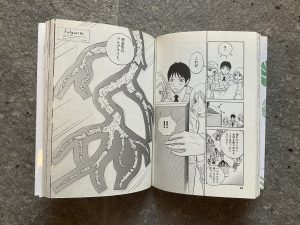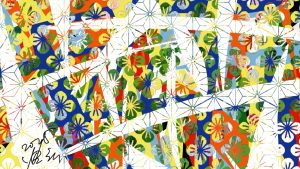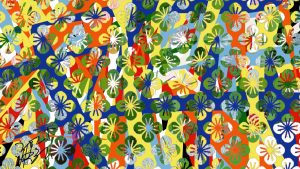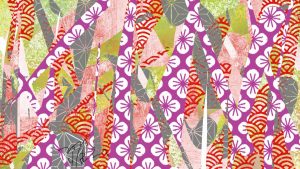高校野球のピッチャーB君、右肩の前側(三角筋前部繊維といいます)、左腰痛そして、走塁の際、急に止まって左足首内側に痛みがあります。
「3カ所のうち、どこが一番気になるの?」
「肩です!」
「そしたら、ベッドで(治療を)やろう。」
と奥のベッドに移動して、臀圧(デンアツ=母校が見つけたお尻の側部のツボ)、居髎(キョリョウ=骨盤の前面のツボ)、五枢(ゴスウ=骨盤の上部内側のツボ)に置鍼。
「これで、肩どう?」
「・・・・・え?・・痛くないです。凄い!」
と、ニッコリ笑顔。
「そしたら、今度は足首を狙おうか!」 (つづく)