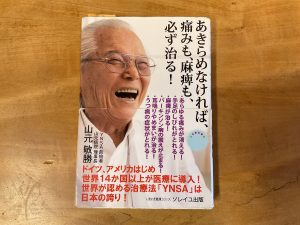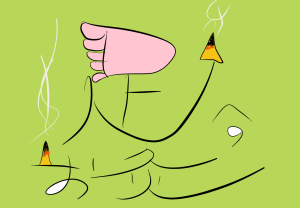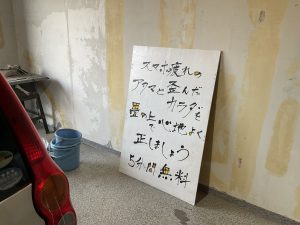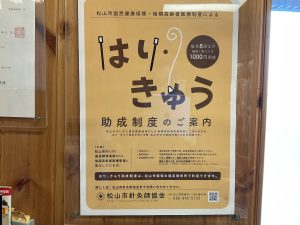今日も入道雲が湧き上がる真夏日だったのですが、早朝には、結構な雨が降り続けました。ヒマワリに水をやることもなく、9時からの患者さんをお待ちしていたのですが、その患者さん、バイクに乗って来られました。半袖から見える腕が濡れているので、すぐさまタオルを用意して腕を拭いていただきました。
「上は、カッパをかぶってたんで、大丈夫だと思います。」
「そうですか・・・あれ?やっぱり結構濡れていますよ・・・着替えましょうか?」
幸い、以前は患者着(かんじゃぎ)に上下はき替えていただき、治療をしていたので、沢山患者着を用意しています。そこで、今では音楽関係の物置のようになった着替え室で上下ともはき替えていただきました。60才代の男性患者Aさんの濡れたシャツとジーンズを着替え室で干すことにしました。普段、治療している患者さんに風を送っているサーキュレーターを移動して、濡れたシャツとジーンズに風を当てました。
治療が終了して、シャツとジーンズの乾き具合をみてみると、ジーンズは良いのですが、シャツがまだ濡れています。そこで、アイロン掛けをすることにしました。当院は、中央部に3畳ほどのタタミ部屋が40cmの高さであります。そこに大きなタオルを敷くと、大きなアイロン台になるのです。普段は、私が操体法をしながらカラダと向き合う場所なのですが、アイロン台で、その上4つの引き出しがあるので、鍼やカルテやクッションの保管庫でもあります。
そこで、シャツにしっかりアイロン掛けして、気持ちよく着替えていただきました。もう患者着を使うことはないだろうと思っていたのですが、このような緊急時には役に立つのです!めでたし、めでたし。