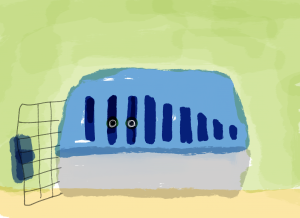高校時代の野球部先輩が、お酒を持って来院されました。私が1年生の時の3年生で、小さな大投手でした。県大会ベスト4までの立役者。私は、その時まだ柔道部に所属していたので、実際には、一緒に練習したことがなかったのに、随分お世話になっています。大学受験の時、部屋に泊めて頂いたり、東京を案内してもらったり・・・・そして、地元に帰ったら、母校松山東高校のOB会や、の・ボール野球に誘っていただいたり・・・・お世話になりっぱなしです。
今日は、「京ひな 一刀両断」という純米大吟醸をいただきました。仕事が終わったので、これから呑んでみます・・・・・・これは、美味い‼️マッタリ、サラッとして上品・・・・これは、いけます‼️
昔の街並みが残っている内子町の「酒六酒造株式会社」が、製造元です。そこで、インターネットを調べてみました。
白壁と木蝋の町並みが、愛媛県屈指の観光地である内子町の中心部に位置しており、澄んだ空気と小田深山渓谷からの豊かな水の恵みを活かした酒造りをしています。内子町では古くから小規模ながらも酒造りが盛んで1920 年(大正 9 年)に地元8名の酒造家が集まり喜多酒造の名 で「京ひな」を醸造。1941年(昭和 16 年)に引き継いだ酒井繁一郎が、紡績業を興した父の酒井六十郎にあやかり 「酒六酒造」と社名を改め、今日に至ります。 商標「京ひな」は、京都の名僧がお酒を飲み、賞賛した日が「ひな祭り」であったことに由来しているそうです。
私の大好きな内子町、頑張っています❣️