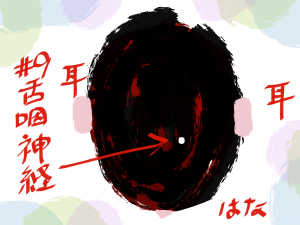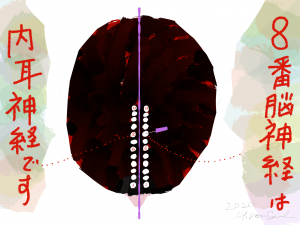中学3年生の女子患者Bちゃん、2年前から来院されていますが、打撲や筋肉痛の治療がほとんどでした。しかも、「鍼治療」がこわいので、筋膜はがしや指を軽く皮膚に触れる治療しかしていません。ところが、今回は意を決して「鍼治療」に挑戦することになりました。
家族の方々が当院で「鍼治療」を受け、特にBちゃんのお兄さんが、良くなったのが大きかったようです。また、松山市作成の「はり・きゅう助成金のご案内」が一役買ってくれました。
多くの方は、鍼灸治療は、肩こり、腰痛だけに効くものだと思われているように思います。
ところが、この「ご案内」では、1:整形外科系の病気 2:脳神経系の病気 3:循環器科系の病気 4:呼吸器科系の病気 5:消化器科系の病気 6:耳鼻咽喉科・口腔器科系の病気 7:泌尿器科系の 8:眼科系の病気 9:産婦人科系の病気 10:小児科系の病気 11:内分泌科系の病気 12:皮膚科系の病気に対応できることを紹介しています。
これを知った家族の方が、Bちゃんの喘息(ぜんそく)を心配しての今回の来院となりました。
Bちゃんは、去年の夏には、過呼吸症候群になり入院。今でも、深呼吸が出来ません。また、右腕と右肩甲骨に痛みがあります。そこで、頭の鍼の説明をBちゃんにしました。
「最初、脳と背骨を刺激するツボに鍼をして、自律神経を整えますね。自律神経というのは内臓の働きを整えるんで、喘息(ぜんそく)にも効くけんね。そして次は、首を診(み)て、12の内臓状態をチェックして、治療します・・・・鍼を打つのは、オデコと頭の横の部分(側頭部)になるけど、大丈夫?」
「はい。」
Bちゃん、すっかり腹を決めています。
「そして、そのあと右の肩甲骨をみましょう。」
「はい。」
まず、合谷診(人差し指と親指の間の触診)から始めます。明らかに左手に痛みがあります。そのため、治療は左側から行います。次に、進化系合谷診(人差し指につながる中手骨を6等分し腰椎、胸椎、頸椎、大脳、脳幹、小脳を診断します)。
下記のように、頸椎、胸椎、腰椎、脳幹、大脳に対応する個所に圧痛点がありました。この6等分された中手骨のそれぞれの圧痛点がなくなれば、それに対応する個所が治療出来たことになります。下記の( )内の数字は、圧痛点がなくなった置鍼の数です。(0)は、他の置鍼の影響で圧痛点がなくなったことを示します。これで基礎治療が終わり、自律神経が整いました。
左:頸椎(1)、胸椎(1)、腰椎(0)、脳幹(1)、大脳(1)
右:なし
初めての鍼治療ですが、じっとガマンして一言もしゃべらないBちゃん。続いて、首診で12内臓点を診断します。これは、首にある12の診断点を押圧して、圧痛点を調べ側頭部にある治療点に置鍼し、圧痛点を取っていきます。その結果が、下記の通りです。
左:腎(0)、心包=心臓の周辺(0)、心(0)、大腸(1)、胃(0)、脾(0)
(0)は、大腸点に置鍼したため、その影響で圧痛点がなくなったことを示しています。
ここまで、Bちゃん頑張っています。1本の置鍼でその他の内蔵点も良くなりました。
「Bちゃん、よう頑張っとるな・・・偉い。」
今度は、右側。
右側頭部のこめかみ付近に置鍼。すると、Bちゃんの目が急に赤くなり、まぶた周辺も赤くなって、大粒の涙があふれて・・・
「ごめんね~、痛かったか・・・・そうか、痛かったら、泣くんじゃ・・・」
思わず子供の素直さを驚いて、言わなくてもいいことをしゃべってしまいました。
右:腎(1)、膀胱(1)、大腸(0)、三焦=消化器(0)、小腸(0)
腎、膀胱の置鍼は、確かに痛い時があります・・・Bちゃんよく頑張りました。右肩の痛みが少し残るくらいになりました。そこで、オデコの中央部で生え際にあるB点に1本置鍼。
「どう?・・・肩」
「・・・・痛くない!」
泣きべそだったBちゃんの顔が一気に笑い顔。そして・・・
「あっっっ、深呼吸出来る‼️」
ますます笑顔のBちゃん・・・・ホントによく頑張りました、めでたしめでたし。