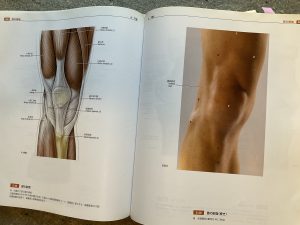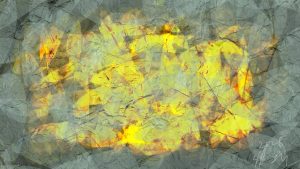
夏大根は、辛いそうなのですが、輪切りにし干して長期保存するつもりです。
私が幼い頃、ばあさんが作った乾燥した大根をだし汁で甘辛く炊き、唐辛子がチョット入った味を思い出したからです。そこで、保存方法をコピペします。
『干し野菜全般のコツとしては、朝起きたら干して、夕方帰宅したら取り込む……
洗濯物と同じ感覚ですね。細かいサイズのものなら半~数日で、丸干しの場合は2週間ほどかけてお好みの乾燥具合に仕上げます。
もし出しっぱなしにしたい場合は夜露がかかりますので夜間は上にカバーをかけてあげればOKです。
干す場所は陽の当たる場所で風通しの良い場所‥‥‥つまりこちらも洗濯物と同じになります。』
ということで、2枚あるムシロを1枚は、カバー用にすると便利なことが、分かりました!また、乾燥した大根は、小さめのナイロン袋(180mmx250mm)に乾燥剤とともに入れ、冷蔵庫の野菜室で保存すればいいようです。






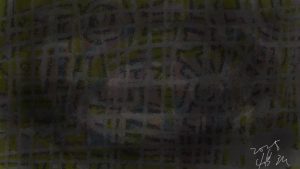



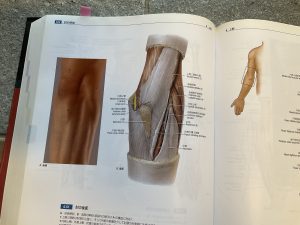 j
j