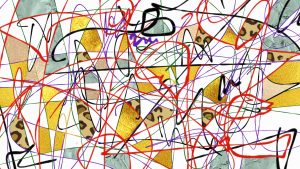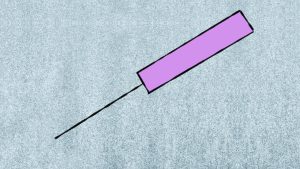
昨日は、記念すべき日となりました。令和6年6月11日、「鍼1本の日」と制定いたします。
山元式新頭鍼療法(YNSA)を治療法として、5年。未だかつて1本の鍼だけで治療を完結したことはありませんでした。小学校5年生の捻挫を2本の鍼で治療したのが、最少本数でした。ところが、昨日は、1本の置鍼で頸椎から仙骨にかけての背骨が整ってしまいました。
60才代の男性患者Cさん。長時間歩行すると腰痛が発生する間欠性跛行(かんけつせいはこう)という病名で来院され、8ヶ月目になります。膝診、首診の基本的な治療を行なっていくうち、Cさんのカラダは徐々に良くなっていったようで、
「特に、痛いところはありません。」
という報告を受けることが多くなり、最近では3週間に1度の通院になっています。その結果、昨日の膝診は、頸椎、胸椎、腰椎の圧痛点が顕著にあるだけで、首診(内臓の状態を診断する)には反応がありませんでした。今考えると、鍼1本で良くなる条件は整っていたようです。そこで、1番気になったのが胸椎1~2番。膝ウラの内側がゴリゴリしています。
「これを取れば・・・・面白い!」
と思ったのでしょう、いつのまにか膝ウラ内側に手がいっていました。その治療点を見つけ置鍼。
「どうですか?」
「・・・・・っぱっ!ははは・・・痛くない!」
「そしたら、ここ(膝診の別にある診断点)は?」
「・・・あれ?ははは!」
診断点全てから圧痛点が消えてしまいました。
「Cさん、今日は記念すべき日です。初めて1本の鍼で治療終了となりました。」
この日は、これからの治療人生でのターニングポイントになるかも知れません。