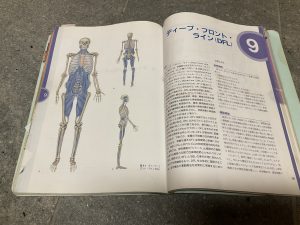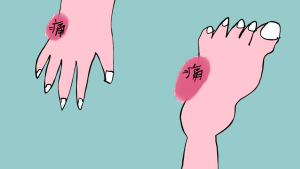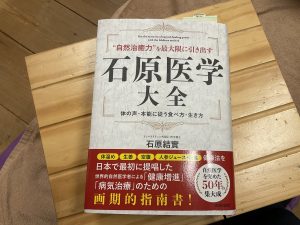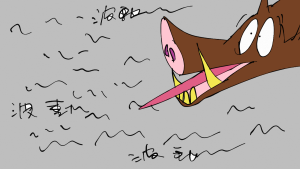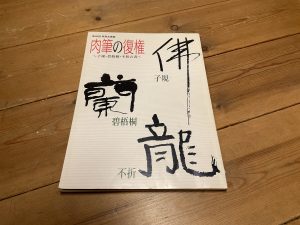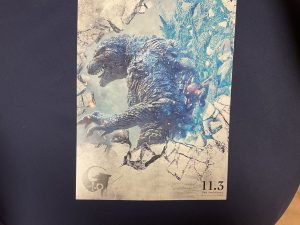鍼灸は保険が効かないの?との質問があり、「医師の同意がないと、効きません」とお答えしていました。実際、近くの病院で同意書をお願いに行ったのですが、書いていただけませんでした。それで、「無理だ!」と決めつけていたのです。ところが、あんま、マッサージ、指圧の同意書を医師から受け取り、施術を受けておられる患者さんの存在を知りました。そこで、調べてみると、やはり、鍼灸でも可能であることが分かりました。
下記は、ある組合のホームページのコピペです。
『医師の同意をうけ同意書がある場合に限り、はり、灸、 マッサージの施術が決められた範囲内で受けられます。 また、はり・灸・マッサージの施術についても、 同一疾患について病院・医院で治療を受けている場合は、保険証は使えません。
●はり・きゅう施術…神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症 等の慢性的な疼痛を主症とする疾患
保険医の同意と再同意
まずは医療機関で保険医による診察を受け、施術について同意書の交付を受けてください。保険医による同意書に基づく療養費の支給が可能な期間は6ヶ月です。
施術期間が6ヶ月を過ぎた場合、再同意書(文書)の交付が必要になります。』
そこで、3月9、10日に研修を受けた後、4月から医師の同意書を持った患者さんからは、保険適応が可能になるシステムを作る予定です。