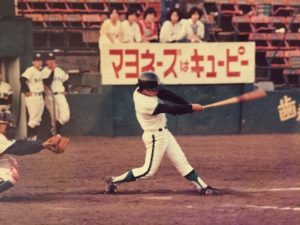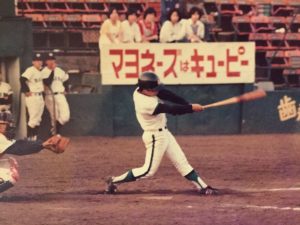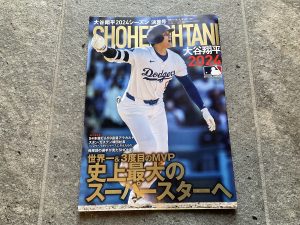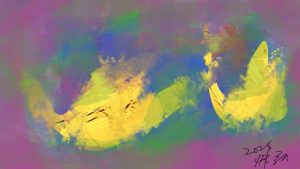「先生の治療受けて2~3日、調子ええんよ。でな、調子に乗りすぎて草引きやら、色々動こう?それで、また右肩が痛とうなるんよ。」
「う~~ん。分かった、そしたら今日は、横向きになってもろて、いきなり腰を押してあげらい。」
ということになり、80才代の女性患者Aには、腰の大切なツボを中心に、仙骨周辺もしっかり押圧することにしました。
「先生、よう効く・・・・気持ちがええ!」
「気持ちのええんが一番よ!気持ちようて治るんじゃったら最高じゃろ?・・・・で、どうなん?・・肩?」
「・・・あれ?どしたん・・・痛ない!先生は、腰を押しとるだけじゃのに?」
「あのね、肩と腰が引っ張りあいしとるんよ。ほじゃけんな、腰がゆるむと肩もゆるむようになっとるんよ。簡単じゃろ?」
「そんなもんね?・・・ほじゃけど、今度は首の根っこの方が痛なった!」
「う~~ん、そうなん。そしたらここ、押してみようわい・・・人体実験。」
「人体実験?!」
「そうよ、人体実験・・・どう?」
「・・・・・・あれ、ようなっとる。」
「やっぱり!」
などと、取り止めのない会話が続く治療でした・・・・おしまい。