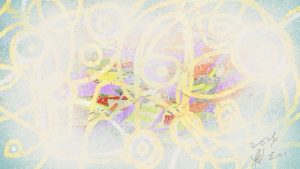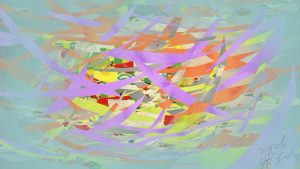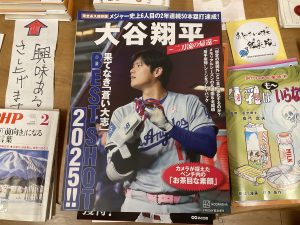140才代の男性患者Aさん、初めての来院です。重い物を運ぶことが多いため、ガッチリとした体躯(168cm、90kg)をされています。1ヶ月前、朝起きて肘を後ろに引くと肩の前から胸にかけて痛みがありました。その痛みが今も続いています。そこで、ベッドに仰向けになってもらいます。
確かに右肩と右前腕部が固まっている感じで、右脚が2cmほど短くなっています。そこで、右肩、右前腕部を「痛気持ちいい程度」で押圧すること、3~4分。これだけで、左右の脚がそろい、骨盤が整います。今度は、右肩を上にして横向きになってもらいます。
「下の脚をまっすぐにして、上の脚を90度に曲げてもらってよろしいですか?」
と、右臀部が安定した状態を作ってもらいます。主要なツボを押しながら太ももの外側(腸脛靱帯)を押圧・・・・・?普通なら、必ず痛がる個所。
「どうですか?痛いですか?」
「いいや、全く痛くないです。」
「えっ!・・・そうですか・・全く痛くない?」
「はい。」
多くの患者さんが痛がる個所なのに、全く痛くない。これは、Aさんが普段取っている体勢と動きに関係があると思います。重い物を運ぶ時「足は親指、手は小指」という重心安定の法則で動いていますが、長時間反復すると、「過ぎたるは及ばざるがごとし」大腿部内側に圧力がかかり過ぎているのだと思います。そこで仰向きになってもらいます。
「ここ(大腿部内側)は、どうですか?」
「痛い!」
やはり、ポイントは大腿部内側。特に大きな大腰筋が関係しているはずです。Aさんは、肩の三角筋の前側から大胸筋にかけてに痛みがあるので、その治療個所は、体幹と太ももをつなぐ「大腰筋」と推測します。(つづく)