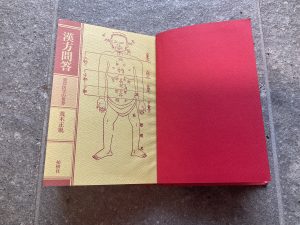パーキンソン病が、増え始めたのはいつ頃からですか?とチャットGPTに尋ねると、
『「古くからある病気」ではありますが、信頼できる統計で 明らかな増加 が確認されるようになったのは 1980年代以降、特に1990年代~2000年代あたり からです。そしてその増加は現在も続いており、今後も高齢化などによってさらに患者数が増えると予想されています。』
と説明してくれました。そして、バブル期と関係がありますか?と再び尋ねました。すると、
『パーキンソン病の症状のピークが年齢60~70才代。バブル期(1986~1991)に20~40代だった人は、現在この好発年齢に入り始めています。つまり、「バブル期の世代が年を取り、患者数が増えている」という“時代の重なり”はありますが、因果関係ではありません。』
とありました。しかし、バブル期に飽食し、消化器に血液が回り、大切な脳に血液が流れておらず、なおかつ、その飽食が今なお続いているならば、因果関係があると考えても良いようにも思えますが・・・