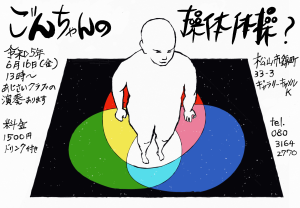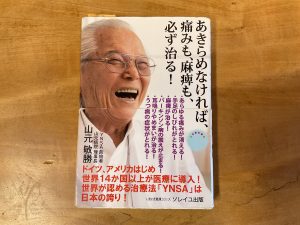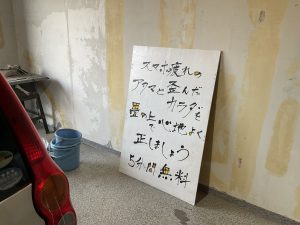どうやら、ヒマワリの育て方、ちょっと間違えていたようです。下記のように、「本葉4枚ぐらいの小苗のうちに1度摘心して育てると、姿よく咲かせることができます。」とあります・・・・あらら、摘心をしないと上手く咲かないようです。どうしよう・・・・今、外に出てある程度大きくなったヒマワリの摘心を4本ほどやってみました。さて・・・・どうなることやら・・・
『日当たり、水はけのよい場所が適地です。ヒマワリは荒れ地でも育つ丈夫な草花ですが、よく作るためには、有機物を多く含む肥沃な土にして作るようにします。
草丈と同じくらい根が深く伸びるので、深さ40cmくらいまで耕し、堆肥、腐葉土、元肥をすき込むようにします。
ポットに根が回ったら、苗が老化しないうちに定植します。ヒマワリは生長が早いので、肥料切れしないよう月に1度、追肥を与えるようにします。
なお、中高性種は、本葉4枚ぐらいの小苗のうちに1度摘心して育てると、姿よく咲かせることができます。
蕾が見える頃になると、地上部が重くなり、倒れやすくなるので、支柱を立て、誘引します。
梅雨明け後、晴天が続いて土が乾くと下葉が落ちやすくなるので、株元に敷きわらをし、乾きがひどいときは週に1度、たっぷり水をやるようにします。
分枝の多い小輪咲きのヒマワリは、終わった花を切り取るようにすれば、株が弱らず、長く花が楽しめます。
熟した種は、食用になります。また、実のついた枝を取り、ドライフラワーとしても楽しめます。』