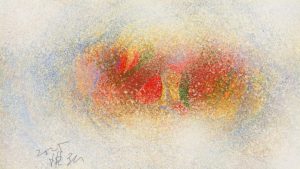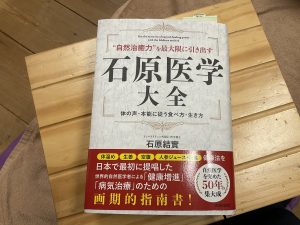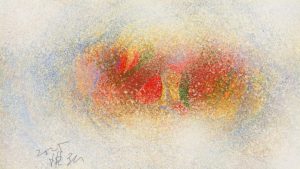
最近、五十肩やボールの投げすぎ、仕事の都合での肩痛と、肩の治療が多くなっています。そこで、手っ取り早い施術として痛い肩と同側のお尻の筋肉を緩めることをしています。
お尻には大まかにいうと、大臀筋、中臀筋、小臀筋という目立った筋肉があり、その奥に梨状筋をはじめとする小さな筋肉があります。
山元式新頭鍼療法(YNSA)では、肩が痛い場合は、腰で治療をする方法があります。これは、カラダの中心ヘソ(母と子の生命の絆を結んだところ)を基準として人が大の字にねっ転がり、ヘソからの同心円を描いたとき、レオナルド・ダ・ヴィンチの人体図のように足首は手首と同心円を接します。このイメージ(あくまでイメージです)で、腰と腰に対応する肩の相似形を考えてみましょう。
腰は、仙骨、腸骨、坐骨、恥骨があります。肩は仙骨に対応する骨は、ありませんが、腸骨に対応するのが肩甲骨、坐骨に対応するのが鎖骨、恥骨に対応するのが胸骨。と、勝手に考えます。今回は腸骨、坐骨と肩甲骨、鎖骨を相似形としてそれらに関係する筋肉を対比します。すると下記のようになります。
大臀筋=三角筋後部繊維 中臀筋=三角筋中部繊維 小臀筋=三角筋前部繊維
梨状筋=棘下筋
上記の関係から大臀筋にあるツボ(経穴)=臀圧(でんあつ)・環跳(かんちょう)・胞こう を三角筋後部繊維の治療点と考えます。
小臀筋辺りにあるツボ(経穴)=居髎(きょりょう)・別説、環跳(かんちょう)を三角筋前部繊維の治療点と考え、三角筋中部繊維は、上記2つの治療点の間にある圧痛点とします。
こんな感じで、お尻の押圧をすると肩痛がウソのように良くなります。ちょっと、専門的になってしまい申し訳ありませんでした。