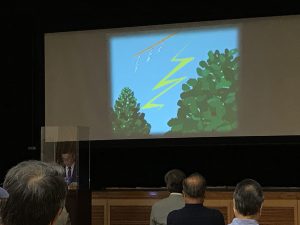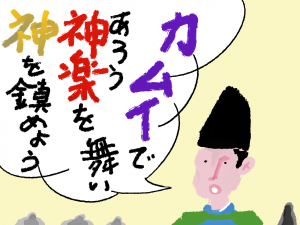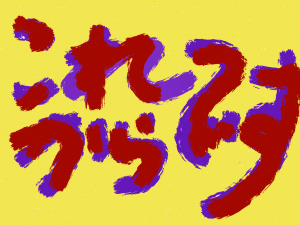1才になるかならないかのオス猫のチャルルは、我が家を別荘として悠々(ゆうゆう)と過ごして、2日目です。我が家が前回と少し違ったのは、2本の物干し竿に吊り下げた服の数です。となりの部屋に吊り下げていた服を全てもってきたのです。そのため、この畳部屋は大きなクロゼットともいえるでしょう。
チャルルが最も好きな場所が、部屋の隅(すみ)にある大きな戸棚の天辺。そこから見渡す風景には、私はいなくてたくさんの服が雲海(うんかい)のようになっているはずです。多分気持ちいいはず。私は普段、畳部屋(小さなビルの2階)にはおらず、1階の治療室にいるため、チャルルが部屋の王様。私がたまに帰って来て、白衣を物干し竿に掛けます。掛けた白衣を取ろうとすると、
「シャ~~~(オレのテリトリーに何してる!)」
と威嚇(いかく)が始まるのです。チャルルにとっては服の雲海もテリトリーですから、どの服に触れても威嚇(いかく)されます。こちらとしても、「主人はこっちじゃ」というオスのプライドがあるので、「ひとケンカ」。
次回は、服をとなりの部屋に大移動することにしましょう(*^ω^*)