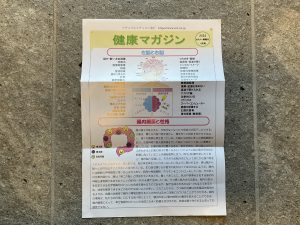 今回も、大沼四廊先生主催の「ナチュラルメディスン」発行のチラシの一部を紹介いたします。
今回も、大沼四廊先生主催の「ナチュラルメディスン」発行のチラシの一部を紹介いたします。
『腸内環境を乱す危険なもの
抗生物質:抗生物質が市販されていないのは薬物乱用を引き起こし、結果的に薬物耐性菌の問題が出てくるため。医師が処方する場合でも、不必要な抗生物質の処方や間違った処方の仕方により耐性菌が問題となっている。抗菌剤はお腹の中の腸内細菌の善玉菌を壊し下痢の原因になる。幼少期にたくさんの抗菌剤を出された子供たちは、心身の具合が悪いまま成長し様々な疾病発症のリスクが高いと言われている。
非ステロイド性消炎鎮痛薬:炎症の局所におけるプロスタグランジンなどの活性物質の抑制によって、解熱作用、鎮痛作用、抗炎症作用を発揮する。一般に「痛みどめ」と称される薬剤を言うが、障壁にダメージを与えるリスクが高い。
遺伝子組み換え食品:人体が毒素を解毒する力を弱める。
脳の健康に大切なビタミンDの機能を弱らせる。
トリプトファン及びチロシンの合成を阻害する。
農薬(農薬と塩素):メタン菌が増殖し、肥満、歯周炎、大腸がん、などのリスクを高める。
合成化学物質:ペットボトルなどに使用されるビスフェノールはホルモンバランスを乱すことが知られている。これらの合成化学物質は、内分泌腺や脂肪組織に蓄積する。当然に肝臓の処理機能を上回り、毒素を排出することが困難になり、体全体の働きと腸内環境のバランスを大きく狂わせることになる。
食品添加物:天然や自然由来でないケミカルなものは、体内に徐々に蓄積されていく。当然に腸内環境とも折り合いが難しく、体内に毒素を蓄積することになる。解毒係の肝臓に当然大きな負担となる。』
プロスタグランジン、トリプトファン、チロシンなど専門学校ではならいましたが・・・よく分かりません。カタカナのところは無視して、それなりに読んでください。
抗生物質に関しての記事をコピペします。
『抗生物質は古来より使用されてきた。複数の文明がカビなどを感染症の治療に使用しており、古代エジプト、ヌビア、ギリシャなどでその記録が残されている。20世紀の初頭にポール・エーリッヒらが合成抗菌薬を開発したことで選択毒性に基づく感染症の化学療法という概念がもたらされる。そして、1928年にはアレクサンダー・フレミングが世界初の抗生物質であるペニシリンを発見、ハワード・フローリーとエルンスト・ボリス・チェーンの研究により大量生産が可能になったことで普及が進んだ。その後、抗生物質の開発は1950年代から1970年代に黄金期を迎え、グリコペプチド系、ホスホマイシン、マクロライド系など、様々なクラスの抗生物質が発見されていった。』
『抗生物質の有効性と入手のしやすさから、不適正な使用につながり、一部の細菌は抗生物質に対する耐性を進化させた。 複数の抗生物質に対し耐性を示す多剤耐性菌の出現を受けて、世界保健機関は抗生物質が効かなくなるポスト抗生物質時代の到来を危惧している。このような背景を受けて、近年は土壌以外の環境から抗生物質の探索を行う試みが進められているほか、抗生物質に依存しない代替製剤の開発も進められている。』







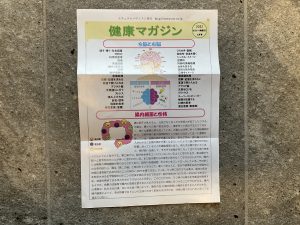

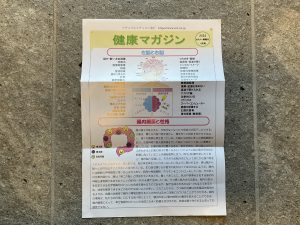 今回も、大沼四廊先生主催の「ナチュラルメディスン」発行のチラシの一部を紹介いたします。
今回も、大沼四廊先生主催の「ナチュラルメディスン」発行のチラシの一部を紹介いたします。