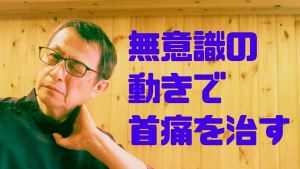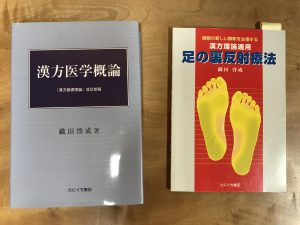60才代の女性患者Aさん、2年前から脊柱管狭窄症と腰椎すべり症と診断されました。そして、今年2月から左腕が上がらなくなり、今一番気になっています。そこで、合谷診(親指と人差し指の間の触診)をすると、左側が痛い(左側にカラダが偏っていると解釈しています)ので、左側の自律神経を整えます(左膝の圧痛点を無くします)。
しかし、左膝の頸椎診断点の圧痛が中々取れません。結局足に6個のパイオネックスを貼りやっと痛みが無くなりました。Aさんが2年前脊柱管狭窄症と腰椎すべり症と診断を受けた時、頸椎の診断点である膝内側(ヒラメ筋)が痛くなったそうです。
脊柱管狭窄症、腰椎すべり症→頸椎診断点(左膝内側痛)→左腕が上がらない
上記に何らかの因果関係があるなら、頸椎診断点の痛みが無くなると、左腕が上がるかも知れません。そこで、Aさんに左腕を上げてもらいました。
「・・・・あれ?上がる・・・・先生、すごい!」
やはり、何らかの関係があったようです。後は、胸椎診断点と腰椎診断点の圧痛を5個のパイオネックス(皮内鍼)を足に貼ることで解消しました。念のため、もう3個パイオネックス(皮内鍼)を貼って終了となりました。操体法の師匠である今昭宏先生が、「患者さんは、治療院に学ぶために来ている。」とおっしゃいました。私もその通りだと思い、出来るだけ分かりやすく治療の内容を患者さんに説明しています。
診断名がつくと、患者さんはその言葉に縛(しば)られるようになりますが、私はその呪縛(じゅばく)を取るようにカラダの説明をします。
「カラダの60~70%は水で出来ていて、骨は水袋に浮いています。その骨を筋膜が支えています。」
と言って、ヘチマタワシをトンスケ(ガイコツ)の上腕につけたものを、筋膜と見立て、筋膜の説明をし、骨は骨芽細胞と破骨細胞が働き3年で全ての骨が新しくなる事もいいます。
「例えば、肩甲骨の筋膜がねじれて緊張すると、骨盤の筋膜もねじれて緊張し、引っ張りあってバランスを取ります・・・・・だから、一方がゆるむと、もう一方がゆるむんです・・骨って簡単に動きます・・・水に浮いているんですから。」
などと、説明すると納得してもらえます。山元式新頭鍼療法(YNSA)が頭や足に置鍼して治療することも、これらの説明や自作のYouTubeを見ていただき、理解してもらっています。