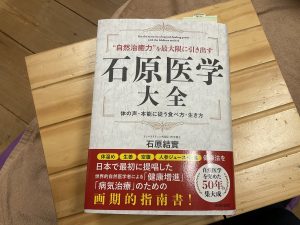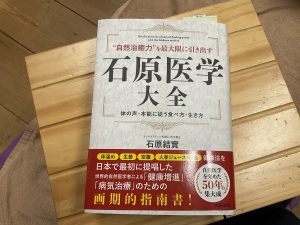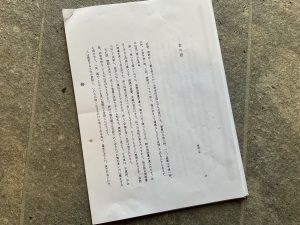70才代の男性患者Aさん。ほぼ毎日、ご夫婦で30分間散歩をしておられるそうです。ところが、そのたびに、肩甲骨がだる重くなってしまうそうです。
「う~~ん、歩くたびに肩甲骨が痛くなる・・・・・・・どんな姿勢で歩いているんですか?」
「普通ですけど。」
「あの~、着物を着てワラジを履いていたころの日本人の歩き方をすれば、自然な歩き方になるんですが・・・・・肘は内側を向いていますか?」
「普通に腕振っているんで、肘は外向いてるかな?」
「そういう姿勢だと、肩肘が張って肩甲骨も痛くなってきます。ちょっと、待ってください、着物を持ってきますね。着物を着て歩いてもらいます。」
ということになり、普段私が着ている着物を持ってきて、着ていただくことにしました。
「どうですか?」
「そうじゃね・・・歩幅が狭なって足があまり上がらんな。」
「そうでしょう・・・昔の日本人は、肘や膝を緩めて、能舞台を歩くような感じであるいてたんですよ、これだったら肘が内向いて肩甲骨が張ることないです。」
などと、話しながら歩く姿勢を考え直していただきました。奥様も患者さんとして来られるので、お二人で少しずつ修正していただければ!と願っています。