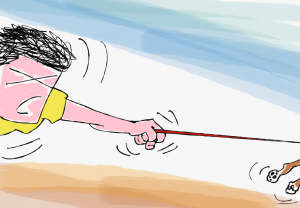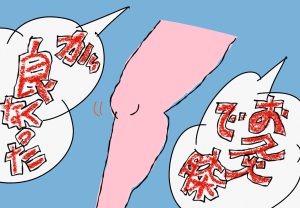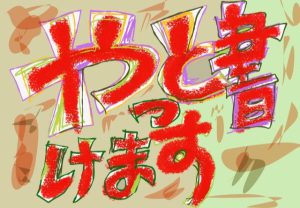「鍼とお灸はどちらが好きですか?」
「鍼です!」
と間髪入れず返事が返ってくる70才代の女性患者Aさん。鍼だけで治療することにしました。目の奥、こめかみ、後頭部、右肩、腰に痛みがあります。こういう場合も自律神経を整えたあと、内臓を整えてからAさんの訴えている箇所の治療をします。
合谷診:右(右上腕診、右膝診をする)
上腕診:右頚椎、右胸椎、右腰椎(1)、右脳幹(0)
膝診:右頚椎#1、#2(1)、#6(1)、右胸椎#1、#2(1)、#9~#12(1)、右脳幹(0)
首診:右膀胱(1)、右肝(0)、右胆(1)、右脾(0)、右小腸(0)、右肺(1)、左腎(3)、左肝(1)、左胆(1)、左三焦(1)、左胃(1)、左脾(1)、左小腸(0) ( )内の数字は置鍼の数。
上記の治療で、こめかみ、後頭部の痛みはなくなりましたが右肩と左目に痛みが残ります。そこで、おでこにあるそれぞれの治療点に、1本ずつ置鍼すると痛みがなくなりました。残る腰痛の治療点(耳ウラ)に2本置鍼。
「あっスッとしてきました。」
随分良くなったようなので、治療終了となりました。後は、
「OKグーグル、タイマー30分お願いします。」
と、置鍼してから30分Aさんにゆっくりしてもらうだけです。私は、Aさんが来院される前にベッドで自力自療の操体法をしていたので、その続きをしたくなり、
「ちょっと、これから体操しますね・・・・」
「・・・はい、どうぞ・・・あのう、見ても良いですか・・・・写真撮っても良いですか?」
「はい、いいですよ!」
ベッドで仰向けになり下肢をゆっくり捻(ひね)ったり、手首をゆっくり回して首肩の連動をうながしたり・・・・
「バシッ・・・・バシッ」
シャッターの音を聞きながら14~5分やったでしょうか・・・・普段のセルフケアを患者さんに見ていただくのは、良いことだと思い、今後は、積極的に見ていただくことにしよう!などと考たのでした。