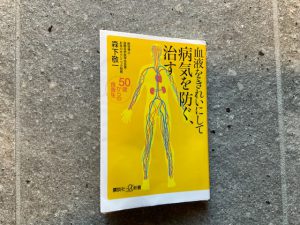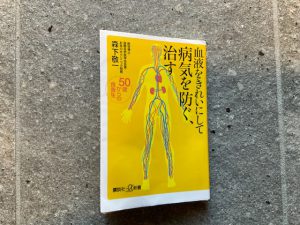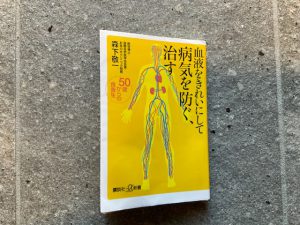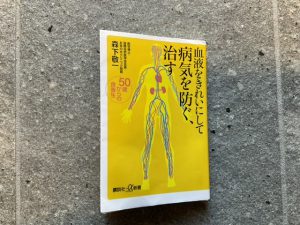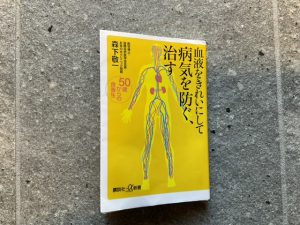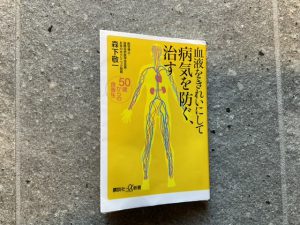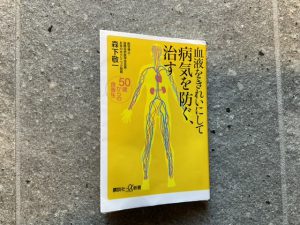「先生、元気になるツボはどこですか?」
「そういわれても、人によって違うし・・・・そんなに、簡単にいえません。」
と返答したのですが、その患者さんが帰られる前に、ヒマラヤ岩塩をお見せし、「これをなめてみませんか?3億8千年前の海水が塩になったものです。」と言って、舐めてもらいました。
「凄い!これ元気になる・・・・・これ欲しい!」
とのお言葉をいただきました。今回は森下敬一先生の「血液をきれいにして病気を防ぐ、治す」の塩に関する一節をご紹介します。
『ネパール人は、紅茶に塩とバターを加えた「チベット茶」を1日に何杯も飲みます。現代の日本人以上に食塩を摂取しているので、現代医学では「非健康的飲茶」といわれることでしょう。しかし、こうした食習慣を持つネパールの人のうち、高血圧症があるのは、小麦を主食とするグループに限定され、ソバを主食とするグループは高血圧症とは無縁です。
塩は人類の歴史と共にありました。海辺に住む人類は、塩の重要性を承知してみずからの手でつくりだしたのです。古代中国の黄帝時代、宿沙氏が海水を煮詰めて塩を作ったといわれます。
この塩は、医薬品として、また、植物及び動物食品の保存料や、日常食生活の食材として供された記録があります。後の「夏(か)」の時代には、一般庶民が塩を食材として購入するようになりました。当時の政府は、これに課税し、財源にしたそうです。
中国の詩人・李白は、塩をひとつまみ舐めては酒杯を傾け「一斗百篇」とたたえられました。またメキシコのテキーラは塩を舐めながら飲みます。牧場の一角に若者が集って、一晩中踊り明かしますが、この時、塩が不足するとたちまちダウンです。しかし、塩の補給が十分なら、ダウンを免れることができます。
人間だけでなく、動物でさえ塩の重要性をしています。ゾウ、ウシ、ヤギ等の野生の草食動物は、岩塩の露出分や塩水の吹き出し口などを知っているのです。夜間には、肉食獣の襲来を覚悟のうえで、その場所に行き、1頭が犠牲になることをと引き換えに多数が塩を摂取します。そうまでして、種属の保存が図られているのです。
このように、塩にはエネルギーが秘められています。その事実を無視し、塩を高血圧と結びつけて、悪者扱いする現代医学に騙されてはいけません。』
ヒマラヤ岩塩を舐めながらのワイン、いけます!動物が生きていく上で、自然の塩は大切のです。しっかり良い塩を取りましょう!