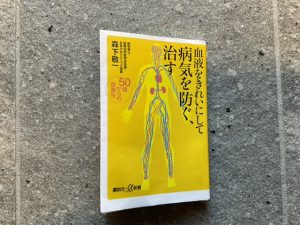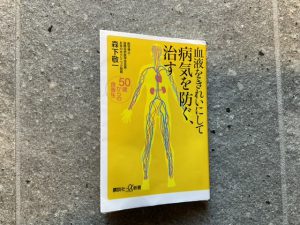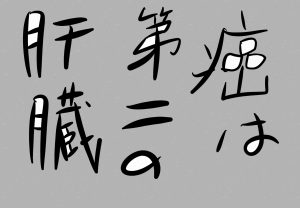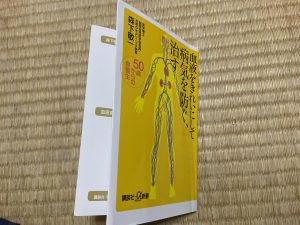最近、仙骨に関心を持つようになりました。理由は3つあります。
1)大野朝行先生(魂合気道の創始者で、カタカムナ研究者)の仙骨呼吸の凄さを体験したためです。
具体的には、YouTube でご確認ください。
2)大沼四廊先生が指摘された腸管膜根(ちょうかんまくこん)という部位は、小腸の根元となり左第一腰椎から右仙腸骨底に位置しています。ストレスのあるカラダは、必ず右仙骨底が縮み上がり、右脚が左脚より短くなっています。これが原因で、様々な疾患が生じることが多いのです。
3)仙骨を解剖学的視点でとらえた時、脊柱起立筋という多層で長い筋肉群の起始(始まる個所)であること。また、筋肉の下には、多数の靭帯が仙骨上に並んでおり、これほど靭帯が多い個所はありません。
そこで、Wikipediaから仙骨の説明をご紹介します。
『仙骨(せんこつ、英: Sacrum)とは、脊椎の下部に位置する大きな三角形の骨で、骨盤の上方後部であり、くさびのように寛骨に差し込まれている。その上部は腰椎の最下部と結合しており、下部は尾骨と結合している。
仙骨となる仙椎骨は、胚発生でははじめの1か月の終わりころに上位の脊椎が先に形成し、その後に形成していく。誕生時の5つの仙椎は、16--18歳ごろから徐々に癒合をはじめ、およそ34歳くらいまでに1つの仙骨として完全に癒合する。』
興味あるのは、「誕生時の5つの仙椎は、16--18歳ごろから徐々に癒合をはじめ、およそ34歳くらいまでに1つの仙骨として完全に癒合する。」というところです。高校生頃から5つの仙椎が徐々に癒合を始め34歳で仙骨になるなんて、全く知りませでした。ということは、ワールドカップで活躍している三笘薫選手、田中碧選手はまだ、仙骨が完成していないことになります。そこで、靭帯が仙椎をしっかり結び付けて腰を安定させているのでしょう・・・今後、もう少し仙椎・仙骨を考えてみようと思います。