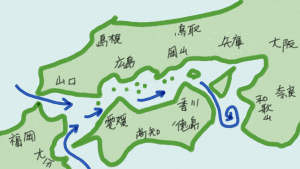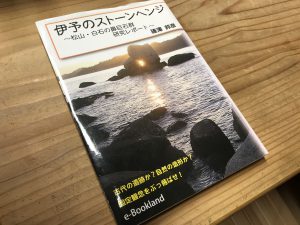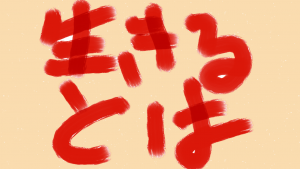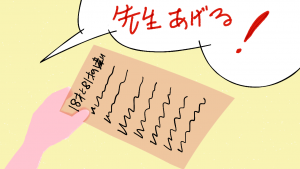あじさいの杜鍼灸院の駐車場は、弟の提案でクスノキのチップを敷き詰めました。夏場は涼しくなり、春から夏にかけての今頃、草が生えてこないことに気づきました。そこで、思い出したのは、私の母校、東谷小学校校庭の大きなクスノキ4本。遊具、砂場、相撲場などがあるところに4本の巨大なクスノキの枝が、巨大な屋根を作って子供達を守ってくれました。
VIDEO
授業の合間の10分間の休み時間、子供達は吸い込まれるようにクスノキの周りに集まり、遊び回るのです。あの場面を思い出すと・・・・クスノキの香りが気持ち良く、草が全く生えていなかった。
私の記憶が曖昧(あいまい)かもしれないのですが、やはり、草は生えてなかったと思います。
クスノキの根っこは、地上に生えているサイズで地下で巨木を支えています。ということは、クスノキの根っこから草が生えない成分が出ているという仮説が生まれても不思議ではありません。そこで、ウイキペディアで調べてみました。
『かつては、木部を採集して樟木(しょうぼく)と呼び、樟脳を採取していた。現代では、自然保護の観点から枝葉を採集して、水蒸気蒸留して粗製の精油を採取している。この精油のことを「取り下ろし油」といい、さらに精製してできる精製樟脳がカンフル(カンファー)である。カンフルを採取した残りの油を樟脳油と呼び、これから防虫剤である片脳油(へんのうゆ)が分離された。またプラスチックの前身であるセルロイドの原料としても用いられた。
古くからクスノキ葉や煙は防虫剤、鎮痛剤として用いられ、作業の際にクスノキを携帯していたという記録もある。樟脳には防虫効果があり、衣類の防虫剤として箪笥に入れられた。また、材は耐朽性が高く、その防虫効果や巨材が得られるという長所から、家具や飛鳥時代の仏像にも使われていた。仏像の材具として、日本では最初にクスノキが使われている。江戸時代には、夏に夕暮れ時にクスノキの葉を焚いて、蚊遣りとしたほか、その煙に包まれて「自然養生にも良きよしと言えり」といった記録が残されている。
薬用
木部に精油が約1%含まれており、有効成分は主にカンフル50 - 60%であるほか、シネオール約6%、ピネン、カンフェン、フェランドレン、ディペンテンなどである。葉にも精油約1%を含み、精油成分はカンフル約50%、サフロール約30%、α-ピネンなどである。
粗製樟脳から精製して得られるカンフルは、強心剤として注射薬に使われるほか、神経痛や打撲に用いる軟膏、チンキ、歯科用フェノールカンフルなど製薬原料として重要である。
民間療法では、疲労回復、肩こり、腰痛、神経痛、リウマチなどの痛みを和らげるために、陰干しにした葉を布袋に入れて、浴湯料として風呂に入れる使い方が知られている。また、1日量1 - 3グラムの木部(樟木)を400 ccの水に入れて30分ほど煎じ、3回に分けて服用する用法が知られる。ただし、妊婦への服用は禁忌とされる。』
とあるように、虫よけや薬としても使われていたのだから、草も生えてこないのだろうと推測できます。