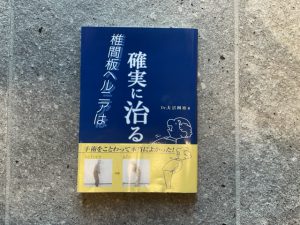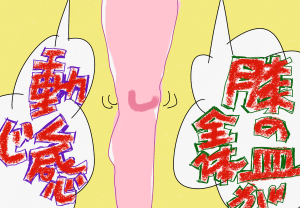(万能ゴムバンドを取った後のリラックスしたAさんの足)
私は、治療という仕事が好きなので、基本的に疲れることはありません。しかし、3日間萬翠荘で制作すると、ものすごい疲れに襲われて、昨日もヘトヘト、今朝おきてもヘトヘト。そこで、大沼四廊先生の万能ゴムバンドを両腕、両脚、頭、タスキ、肩と様々試して徐々に身につけることにしました。やっていく内に馴染んできたので、「これならやれる」状態となり、元気なりました。
「先生、今日はどこも悪ないんよ、調子いい。」
「そしたら、今日は全然違うことをしましょうか?」
ということで、70才代の女性患者Aさんに、万能ゴムバンドでの治療をすることにしました。まず畳間で仰向けになってもらい右ソケイ部を押圧。
「痛い!先生そこ痛い。」
「左(のソケイ部)は?」
「あまり痛くない。」
やはり大沼先生がおっしゃる通り右腸骨が縮んで上に上がっているための痛みです。
『腸管膜根は第一腰椎の左側から右仙腸関節部にかけて斜めに付着しているため、ストレスを受けると収縮して、右側の腸骨を前方上方向に狂わせます。右の骨盤が狂うと右側の下肢を栄養する大腿動脈や静脈が圧迫され右下腹部にうっ血が生じます。』
これは、大沼四廊先生の著書「椎間板ヘルニアは確実に治る」にキーポイントとなる個所として載っている一節ですが、その通りでした。そこで、私が勝手に考案した操法で右ソケイ部の痛みをとりました。この操法は近々YouTubeを制作して紹介するつもりです。大沼先生が50万人以上のがんや難病の方々の体質改善に関与された結果、分かったことは、いかなる病状にも鎖骨下動脈の圧迫があるということでした。
そこで、Aさんの鎖骨と胸骨のつなぎ目(胸鎖関節)を押圧。やはり痛みがあり、左側の方がより痛いそうです。大沼先生によると、このつなぎ目が重症化するほど、癒着し、心臓の出口の大血管が圧迫され、血流が悪くなっていくそうです。確かに、いくら血液の質が良くても、出発点が歪(いびつ)になっていれば、血液が逆戻りしてしまい新たな病気を作ってしまいます。
そこで、Aさんの胸鎖関節や肋骨と肋骨の間を軽くマッサージ。この2つの操法だけでもAさんは調子が良いようです。次に万能ゴムバンドで左脚をグルグル巻き、続いて右脚。
「先生、これすごいね、指が紫色・・・・・先生、力いるでしょう。」
「ホント、いるよ・・・今巻いているところの、動かなくなっているような血液をソケイ部の方に押し上げて、ゴムバンドを下から一気に外して、上の血液を下に流すんです。」
などと説明しながら、行います。今度は骨盤にやや大きめのゴムバンドを締めて骨盤を調整します。これをすると、脚が非常に軽くなり、四股(しこ)を踏むと楽々で出来ます。ついでに細いゴムバンドでタスキがけを軽くして終了。しばらく、大沼先生のYouTubeを2人で見ていると、
「先生、トイレに行きたくなった。」
急いで骨盤のゴムバンドを外してAさんはトイレへ、
「先生、便が出た・・・・治療中にこんなの初めて!」
大沼式万能ゴムバンド、恐るべし。